面白いのではないでしょうか
■小学生もプログラミング=東京・前原小、必修化に先駆け全学年―学習指導要領改定
という記事が時事通信社から発表されました。
プログラミングと言う言葉で表現されだして、注目を浴びるようになりましたが、
こういった試行錯誤的な学習はずっと前より行われていましたね。
ただ、授業と言う形ではなく、特に自由研究という扱いが多い気がします。
決して、目新しい学習方法というわけではないのです。
今の自由研究は、かつての試行錯誤をしながら進める形を失っていて、
本やインターネットで紹介されている実験や観察を、書かれている通りにやってみる、 ただ「確認する」ものになってしまっているのです。
だから、プログラミングと言う言葉で、新たに試行錯誤をして
現象を確認しよう、発見しようという学習を表現しているに過ぎないのです。
学習指導要領では、恐らく、現象を確認するに当たっての手法や段階を予想させ、
現象に応じたチャート、つまり、アルゴリズムを構築できるような力を付けさせたいのでしょう。
ただ、これは強制するのではなく、
教師側には見守るスタンスが求められるのではないでしょうか。
決して、結果を求めない。上手くいかなくても、全然OK。
「好きこそものの上手なれ」と言う言葉があるように、
「なんでやねん!??」と、興味を持ってくれたらその授業は大成功!ってね。
かく言う私も、ファミリーベーシックをきっかけに、
小5のときから実際にパソコンでプログラムを独学していました。
ファミコンみたいなゲームを作ってみたかったから。
今考えると、BASICながら、
FOR I=0 TO A
B=A+I
IF B>C THEN D=RND(B)+I
STR=STR+D
NEXT I
なんて、小学生のくせに理解できてたのがすげーなって、今でも思います。
ソレが高じて、BASICマガジンやOh!Xとか
雑誌で食い入るように研究したものです。
今では16ビットまでなら、C言語やマシン語もOKです(TT)<時代錯誤
けっきょく南極、自分で身につけたその力は、今の仕事にあまり生きていませんが、
ビジュアル機器やソフトの仕組みは、子供ながらに理解できましたし、
今でも通用する知識なので、よかったかなぁと思っています。
プログラミング教育…
アルゴリズムに興味を持つきっかけ作りと言う意味では、
かなりポテンシャルを秘めた教育と言えるのではないでしょうか。
まぁ、うまくいくかどうかは、現行の授業時数と先生方の力との兼ね合いですね。
……教職復帰しようかなぁ…(w

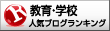
コメント